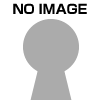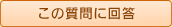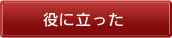編集
someさん、おはようございます。
小さな会社で総務経理をしているものです。
ご質問の件ですが、これは所得税と連動しています。
所得税は個人の所得にかかる国に納める税金です。
所得の計算期間は暦年、カレンダーと同じ1月から12月までの
1年間です。これをその次の年の3/15までに確定申告
(会社勤めで1社からの給与収入しかない場合はその年の
年末調整)で所得税を計算して納めることになります。
この申告書や給与の源泉徴収票の写しが市区町村に
税務署や給与を支払う会社によって送付されます。
これを元に市区町村では住民税を計算し、各人に
住民税の計算書を送る仕組みです。
従って、18年1/1から12/31の1年間の所得を元に
計算した住民税を19年6月から20年5月の間に納める仕組み
です。給与所得者の場合は給与から12分割して納付(端数は
6月分で調整)、事業をやっている人は多分2、3ケ月に
1度、市区町村から納付書も送られてくるので、それで
納めるという仕組みです。
ですので、住民税は約1年遅れの課税になります。
退職した後に収入が0だったり、少ないと、
住民税が後から来るので、支払に苦労したりします。
(これは自分が体験しています)
こんなところですが、何かわからなければまた質問してください。
someさん、おはようございます。
小さな会社で総務経理をしているものです。
ご質問の件ですが、これは所得税と連動しています。
所得税は個人の所得にかかる国に納める税金です。
所得の計算期間は暦年、カレンダーと同じ1月から12月までの
1年間です。これをその次の年の3/15までに確定申告
(会社勤めで1社からの給与収入しかない場合はその年の
年末調整)で所得税を計算して納めることになります。
この申告書や給与の源泉徴収票の写しが市区町村に
税務署や給与を支払う会社によって送付されます。
これを元に市区町村では住民税を計算し、各人に
住民税の計算書を送る仕組みです。
従って、18年1/1から12/31の1年間の所得を元に
計算した住民税を19年6月から20年5月の間に納める仕組み
です。給与所得者の場合は給与から12分割して納付(端数は
6月分で調整)、事業をやっている人は多分2、3ケ月に
1度、市区町村から納付書も送られてくるので、それで
納めるという仕組みです。
ですので、住民税は約1年遅れの課税になります。
退職した後に収入が0だったり、少ないと、
住民税が後から来るので、支払に苦労したりします。
(これは自分が体験しています)
こんなところですが、何かわからなければまた質問してください。
返信