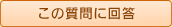昨日悩ましい案件を聞かされ、どうアプローチして行こうか迷っています。
皆さんのお知恵とご意見をお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。
弊社では新しい基幹システムを前期に導入しました。
諸所の問題があった為、期中に支払は起こさなかったものの、未払金を立ててIT税制を摘要した税額控除を行いました。
このソフトはシステム開発を依頼し、2年ほど掛けて作ってもらったソフトで、それなりの値段(数億程度)が掛かりましたが、このソフトが曲者で、導入からエラーを出しまくり、業務にかなりの影響を及ぼしたものですから、先方に損害賠償を求めると言う話が役員方から出ている事は知っていましたが、先日突然損害賠償として数千万円の入金があるから雑収入で処理しておいてと役員方から通達がありました。
すぐに思い付く問題点としては、税額控除したものが否認されないか?と言う事で、次に向こうは損害賠償って言う認識で払ってくるのか?と言う事でした。
ちゃんと裁判をした訳でもなく、どんな話し合いをしたかも分からないので、ただの値引とも取れます。。。
損害賠償と言い張る為にはどんな物が必要でしょうか?
もちろん入金があったものに対しては消費税は非課税にしますが、それだけでは何とも、、、(汗)
色々なご意見を頂けるかも知れないので、よろしくお願いします。
昨日悩ましい案件を聞かされ、どうアプローチして行こうか迷っています。
皆さんのお知恵とご意見をお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。
弊社では新しい基幹システムを前期に導入しました。
諸所の問題があった為、期中に支払は起こさなかったものの、未払金を立ててIT税制を摘要した税額控除を行いました。
このソフトはシステム開発を依頼し、2年ほど掛けて作ってもらったソフトで、それなりの値段(数億程度)が掛かりましたが、このソフトが曲者で、導入からエラーを出しまくり、業務にかなりの影響を及ぼしたものですから、先方に損害賠償を求めると言う話が役員方から出ている事は知っていましたが、先日突然損害賠償として数千万円の入金があるから雑収入で処理しておいてと役員方から通達がありました。
すぐに思い付く問題点としては、税額控除したものが否認されないか?と言う事で、次に向こうは損害賠償って言う認識で払ってくるのか?と言う事でした。
ちゃんと裁判をした訳でもなく、どんな話し合いをしたかも分からないので、ただの値引とも取れます。。。
損害賠償と言い張る為にはどんな物が必要でしょうか?
もちろん入金があったものに対しては消費税は非課税にしますが、それだけでは何とも、、、(汗)
色々なご意見を頂けるかも知れないので、よろしくお願いします。