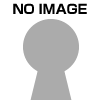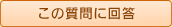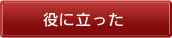いつもお世話になっております。会計士の方になかなか連絡が取れず、以下の処理について困っております。
販促品としてカタログを輸入し一部を得意先に売上げました。
Aカタログ12冊を輸入したとき
aカタログ代 借:販売促進費 貸:預金口座
bカタログ運賃 借:販売促進費 貸:預金口座
c輸入通関費用 借:販売促進費 貸:未払費用
d通関時消費税 借:仮払消費税 貸:未払費用
BAの内の6冊を売上計上するために仕入原価へ振替
e 借:仕入高 貸:販売促進費
C得意先へ売上計上
f 借:売掛金 貸:売上高
※以下の理由のためeの仕訳と同金額です。
以上の仕訳を行ったのですが、今回は利益を取らないことを前提に仕入原価の算出を営業担当者が行ったのですが、実際には支払いが発生していない諸経費を仕入原価に上乗せし、また為替レートの差額も若干あるため、手元にカタログが6冊残っているにも関わらす販売促進費の累計がマイナス計上になってしまいます。
為替レートの差額は仕方ないとしても、支払のない上乗せ経費を利益につなげずに処理するには、どのうような方法があるのでしょうか?
今後も発生するケースとなっているので、どうぞよろしくお願いします。
いつもお世話になっております。会計士の方になかなか連絡が取れず、以下の処理について困っております。
販促品としてカタログを輸入し一部を得意先に売上げました。
Aカタログ12冊を輸入したとき
aカタログ代 借:販売促進費 貸:預金口座
bカタログ運賃 借:販売促進費 貸:預金口座
c輸入通関費用 借:販売促進費 貸:未払費用
d通関時消費税 借:仮払消費税 貸:未払費用
BAの内の6冊を売上計上するために仕入原価へ振替
e 借:仕入高 貸:販売促進費
C得意先へ売上計上
f 借:売掛金 貸:売上高
※以下の理由のためeの仕訳と同金額です。
以上の仕訳を行ったのですが、今回は利益を取らないことを前提に仕入原価の算出を営業担当者が行ったのですが、実際には支払いが発生していない諸経費を仕入原価に上乗せし、また為替レートの差額も若干あるため、手元にカタログが6冊残っているにも関わらす販売促進費の累計がマイナス計上になってしまいます。
為替レートの差額は仕方ないとしても、支払のない上乗せ経費を利益につなげずに処理するには、どのうような方法があるのでしょうか?
今後も発生するケースとなっているので、どうぞよろしくお願いします。