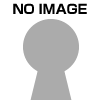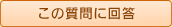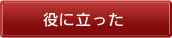実務経験が少ないので教えてください。
銀行勘定調整表についてなのですが、
まず、これは必ず必要なもので決算報告書や申告書に
添付する書類なのでしょうか。
それと、例えば、
未取付小切手があった場合、
当座預金****/買掛金****
というような仕訳で銀行残高に帳簿残高を修正するのだと思いますが、
それとも、小切手を渡した段階で債務は減少したものとして、
修正仕訳を起こさず、その差額を証明するものとして
銀行勘定調整表を作成(添付)するのでしょうか?
実務経験が少ないので教えてください。
銀行勘定調整表についてなのですが、
まず、これは必ず必要なもので決算報告書や申告書に
添付する書類なのでしょうか。
それと、例えば、
未取付小切手があった場合、
当座預金****/買掛金****
というような仕訳で銀行残高に帳簿残高を修正するのだと思いますが、
それとも、小切手を渡した段階で債務は減少したものとして、
修正仕訳を起こさず、その差額を証明するものとして
銀行勘定調整表を作成(添付)するのでしょうか?