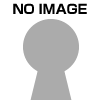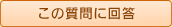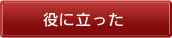編集
会計処理としては、次の2通りの方法が考えられます。
<例>
100円の商品を販売し、10円の割引券と現金90円を受取った。
A.割引券の行使を会計上計上する方法
現金 90 / 売上100
売上値引or販売促進費 10
B.入金額で売上にする方法
現金 90 / 売上 90
単純明快で簡単なのはBの方法です。
これだと会計上も、収益が入金額90であり、消費税の課税売上も90なので極めて簡単です。
Aの方法だと少しややこしくなり、割引券部分の10円を「売上値引」とした場合、最終的には「売上」と相殺消去して決算書には反映させることになります。
(最後に 売上10 / 売上値引10 という相殺仕訳をする。)
この場合、「売上」は90となり、Bの方法とまったく同じ結果になります。
(注:割引券による割引だからといって「売上割引」という科目を使ってはいけません。
割引券による売上代金の減額は、会計上「売上値引」となり、「売上割引」とは別のものです。
この「売上値引」とか「売上割引」というのは、世間一般的な日本語ではなく、会計専門用語ですので、正しく使い分ける必要があります。)
販売促進費として費用処理するという方法もありますが、この場合、会計上は売上収益100、費用10ということになりますね。
その結果、収益・費用の総額は違いますが、当期純利益に与える影響はBの方法とまったく同じです。
消費税の計算上は、課税売上げ100、売上対価の返還10ということになり、やっぱりBの場合と同じ結果になります。
というわけで、どちらでやっても会計上も税法上も同じなので、会社の都合でお好きなほうを採用されるとよいと思います。
(私の知る限りですが、大企業はAのほうで、中小企業はBのほうで経理する傾向があるようです。)
会計処理としては、次の2通りの方法が考えられます。
<例>
100円の商品を販売し、10円の割引券と現金90円を受取った。
A.割引券の行使を会計上計上する方法
現金 90 / 売上100
売上値引or販売促進費 10
B.入金額で売上にする方法
現金 90 / 売上 90
単純明快で簡単なのはBの方法です。
これだと会計上も、収益が入金額90であり、消費税の課税売上も90なので極めて簡単です。
Aの方法だと少しややこしくなり、割引券部分の10円を「売上値引」とした場合、最終的には「売上」と相殺消去して決算書には反映させることになります。
(最後に 売上10 / 売上値引10 という相殺仕訳をする。)
この場合、「売上」は90となり、Bの方法とまったく同じ結果になります。
(注:割引券による割引だからといって「売上割引」という科目を使ってはいけません。
割引券による売上代金の減額は、会計上「売上値引」となり、「売上割引」とは別のものです。
この「売上値引」とか「売上割引」というのは、世間一般的な日本語ではなく、会計専門用語ですので、正しく使い分ける必要があります。)
販売促進費として費用処理するという方法もありますが、この場合、会計上は売上収益100、費用10ということになりますね。
その結果、収益・費用の総額は違いますが、当期純利益に与える影響はBの方法とまったく同じです。
消費税の計算上は、課税売上げ100、売上対価の返還10ということになり、やっぱりBの場合と同じ結果になります。
というわけで、どちらでやっても会計上も税法上も同じなので、会社の都合でお好きなほうを採用されるとよいと思います。
(私の知る限りですが、大企業はAのほうで、中小企業はBのほうで経理する傾向があるようです。)
返信