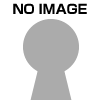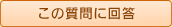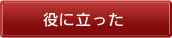はじめまして サイト利用初めてなので よく解らないのですが
解っていることは 支払手形の印紙額を本日間違えたまま遠方の業者さんに郵送してしまってた事です。400円なのに200円貼って送りました。相手にはまだ連絡入れてないのですが、この場合手形は無効になるのか?それとも追加?で200円貼っていいものなのか解りません。相手は東京。こっちは北海道。追加で貼って大丈夫なら、わざわざ郵送する手間をはぶき、「200円印紙貼っておいて」とお願いするのですが、割り印の問題はどうなるのか?とにかく解らない事だらけ。経理初心者、こんなドジだれもやらかさないと思いますが、だれか答えを教えてください。ヘルプ
はじめまして サイト利用初めてなので よく解らないのですが
解っていることは 支払手形の印紙額を本日間違えたまま遠方の業者さんに郵送してしまってた事です。400円なのに200円貼って送りました。相手にはまだ連絡入れてないのですが、この場合手形は無効になるのか?それとも追加?で200円貼っていいものなのか解りません。相手は東京。こっちは北海道。追加で貼って大丈夫なら、わざわざ郵送する手間をはぶき、「200円印紙貼っておいて」とお願いするのですが、割り印の問題はどうなるのか?とにかく解らない事だらけ。経理初心者、こんなドジだれもやらかさないと思いますが、だれか答えを教えてください。ヘルプ