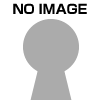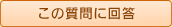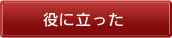ログイン
注目の検索文字列
メニュー
助け合い
経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
減損の兆候とは <至急>

減損の兆候とは <至急>
2011/02/26 00:56
1. Re: 減損の兆候とは <至急>
2011/02/27 20:31
これでわかりますか?
私は経理ではないけれど、なんとなくわかりました。
http://wrs.search.yahoo.co.jp/_ylt=A3aX6DhzK2pNDVsBEWGDTwx.;_ylu=X3oDMTBtbmFianZ2BHBvcwMzBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGU-/SIG=12la01luc/EXP=1298904371/**http%3A//www.aoyamaoffice.jp/school/kaikeischool/genson_kaikei3.htm
これでわかりますか?
私は経理ではないけれど、なんとなくわかりました。
http://wrs.search.yahoo.co.jp/_ylt=A3aX6DhzK2pNDVsBEWGDTwx.;_ylu=X3oDMTBtbmFianZ2BHBvcwMzBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGU-/SIG=12la01luc/EXP=1298904371/**http%3A//www.aoyamaoffice.jp/school/kaikeischool/genson_kaikei3.htm
0
3. Re: 減損の兆候とは <至急>
2011/02/27 23:24
こんばんは。
私は経理ではないし、専門的な勉強もしていないので、専門用語を駆使して説明することはできません。
また、経理についてはあなたのほうが詳しいと思いますので、あなたと私がみたHPから、私なりに理解できたことを書かせていただきます。(理解が間違っているかもしれない)
まず、減損会計とは何かを、私もあなと同じように調べてみました。これがわからないと先へ進めません。
「減損会計は、固定資産の含み損をどう財務諸表上に表面化させるか」ということらしいですね。
その兆候と基準についてHPに書かれていました。一言でいえば、固定資産にかかわる含み損を、減価償却とは別な考え方で簿価から減らす会計処理をするということらしいですね。
(ただし、償却できる範囲内までしか減損処理ができないようですし、税務上損金不算入とも書いてありました)
例えば、土地、建物の減損について考えてみると、その土地の地価が、何らかの事情で(例えば汚染が発見されたとか)、建物が火災にあって人が亡くなったとかの直接の要因で、将来売却してもマイナスになるようなケースについて減損処理をするということだと思います。
(価値が下がって高く売れないはずです。)
これは、兆候というよりも明らかな要因になるんでしょうね。
HPに書いてあったのはこのような直接なものだけでなく、もっとマクロ的なものもこれにあたるということでしたね。
例えば、個別のA事業やB店舗、または会社全体からみたA事業、B、C、D各店舗を一塊とした場合
(HPには資産・資産グループと書かれていた)
その中で固定資産が使用されている場合で、営業成績が悪く利益が回収できない場合(HPでは2期マイナスの場合)、その固定資産が他へ転用できない場合、その固定資産が技術の陳腐化などで利益を生む可能性がなくなった場合などにも減損処理をするようなことが書かれていました。
要は、通常の固定資産そのものの評価損だけでなく、その固定資産を利用しても利益を生めなくなってきた場合にも、その対象固定資産の減損にあたるということが書いてあったのではないかと思っています。
こんばんは。
私は経理ではないし、専門的な勉強もしていないので、専門用語を駆使して説明することはできません。
また、経理についてはあなたのほうが詳しいと思いますので、あなたと私がみたHPから、私なりに理解できたことを書かせていただきます。(理解が間違っているかもしれない)
まず、減損会計とは何かを、私もあなと同じように調べてみました。これがわからないと先へ進めません。
「減損会計は、固定資産の含み損をどう財務諸表上に表面化させるか」ということらしいですね。
その兆候と基準についてHPに書かれていました。一言でいえば、固定資産にかかわる含み損を、減価償却とは別な考え方で簿価から減らす会計処理をするということらしいですね。
(ただし、償却できる範囲内までしか減損処理ができないようですし、税務上損金不算入とも書いてありました)
例えば、土地、建物の減損について考えてみると、その土地の地価が、何らかの事情で(例えば汚染が発見されたとか)、建物が火災にあって人が亡くなったとかの直接の要因で、将来売却してもマイナスになるようなケースについて減損処理をするということだと思います。
(価値が下がって高く売れないはずです。)
これは、兆候というよりも明らかな要因になるんでしょうね。
HPに書いてあったのはこのような直接なものだけでなく、もっとマクロ的なものもこれにあたるということでしたね。
例えば、個別のA事業やB店舗、または会社全体からみたA事業、B、C、D各店舗を一塊とした場合
(HPには資産・資産グループと書かれていた)
その中で固定資産が使用されている場合で、営業成績が悪く利益が回収できない場合(HPでは2期マイナスの場合)、その固定資産が他へ転用できない場合、その固定資産が技術の陳腐化などで利益を生む可能性がなくなった場合などにも減損処理をするようなことが書かれていました。
要は、通常の固定資産そのものの評価損だけでなく、その固定資産を利用しても利益を生めなくなってきた場合にも、その対象固定資産の減損にあたるということが書いてあったのではないかと思っています。
0