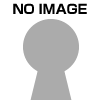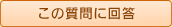編集
以前にも同じようなご質問されていた方でしょうか?
http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=15667&post_id=61518&viewmode=thread#forumpost61518
特別損失は、例えば企業会計原則注解によれば、
(注12)特別損益項目について(損益計算書原則六)
特別損益に属する項目としては次のようなものがある。
(1) 臨時損益
イ 固定資産売却損益
ロ 転売以外の目的で取得した有価証券の売却損益
ハ 災害による損失
(2) 前期損益修正
イ 過年度における引当金の過不足修正額
ロ 過年度における減価償却の過不足修正額
ハ 過年度におけるたな卸資産評価の訂正額
ニ 過年度償却済債権の取立額
なお、特別損益に属する項目であっても、金額の僅少なもの又は毎期経常的に発生するものは、経常損益計算に含めることができる。
上記のように定められています。
経常利益に傷をつけたくないから、特別損失処理で逃げたいというのがトップの指示であれば、
今回の運用悪化による数理差異償却額の増加による退職給付費用計上額の増加は、これに当てはまるという、確信とブレない理由づけを考えるのが経理担当者の仕事ではないかと思います。
さすがに監査法人も、特別損失にしたいから適当な理由を考えてくれと頼んでも、それには加担してくれないでしょう。
単に金額が大きいから、今回は特別損失で処理するというだけなら、通らないと思います。
必死で考えてもやはりこれは無理があると思えば、トップに対して、御希望の処理はできません、コンプライアンスの問題でもありますと、説得するのも経理担当者の仕事だと思います。
以下、「なんちゃって話」をしますので、馬鹿らしいようでしたら無視してください。
最近、売買目的ではない有価証券の評価損を金融商品会計によって減損処理し、これを特別損失に計上するケースが目につきます。
年金の運用がこれと同じだとは言いませんが、もし当該株式を会社が自ら保有していたらその減損は特別損失で計上していたわけで、これを信託銀行などに運用させただけで、実質は会社として減損が発生している・・・だから特別損失でもいいじゃないか・・・とか。
この考え方の弱いところは、年金で運用しているのだから、それは売買目的の株式であって、減損対象ではないと反論されたらつらい。
要するに、何が言いたいかと言えば、
某国がミサイルを発射しても、それは人工衛星であり、衛星軌道上から将軍様の歌を流していると言い張り、世界中から確認できないと反論されても、「心のきれいな人には、ちゃんと聞こえている」と堂々と真顔で言い返す。
会計とは、厳格に規定されているようですが、法規を見ると、けっこうあいまいな表現が多く、複数の解釈がでる事項がたくさんあります。特別なんだ、臨時なんだよ、という理由を自分なりに明確にできたら、某国のように腹をくくって貫き通す、それが重要だと思います。会計士が6対4でこの処理は無理と思っていても、説明自体がブレず、熱意がこもっていたら、勢いで「今回は認めましょう」となったことは、私の思い込みかもしれませんが、あったと思っています。あくまでも6対4の話ですが。
ただ、今回の特別損失処理は、まともに考えたら難しいように思います。
以前にも同じようなご質問されていた方でしょうか?
http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=15667&post_id=61518&viewmode=thread#forumpost61518
特別損失は、例えば企業会計原則注解によれば、
(注12)特別損益項目について(損益計算書原則六)
特別損益に属する項目としては次のようなものがある。
(1) 臨時損益
イ 固定資産売却損益
ロ 転売以外の目的で取得した有価証券の売却損益
ハ 災害による損失
(2) 前期損益修正
イ 過年度における引当金の過不足修正額
ロ 過年度における減価償却の過不足修正額
ハ 過年度におけるたな卸資産評価の訂正額
ニ 過年度償却済債権の取立額
なお、特別損益に属する項目であっても、金額の僅少なもの又は毎期経常的に発生するものは、経常損益計算に含めることができる。
上記のように定められています。
経常利益に傷をつけたくないから、特別損失処理で逃げたいというのがトップの指示であれば、
今回の運用悪化による数理差異償却額の増加による退職給付費用計上額の増加は、これに当てはまるという、確信とブレない理由づけを考えるのが経理担当者の仕事ではないかと思います。
さすがに監査法人も、特別損失にしたいから適当な理由を考えてくれと頼んでも、それには加担してくれないでしょう。
単に金額が大きいから、今回は特別損失で処理するというだけなら、通らないと思います。
必死で考えてもやはりこれは無理があると思えば、トップに対して、御希望の処理はできません、コンプライアンスの問題でもありますと、説得するのも経理担当者の仕事だと思います。
以下、「なんちゃって話」をしますので、馬鹿らしいようでしたら無視してください。
最近、売買目的ではない有価証券の評価損を金融商品会計によって減損処理し、これを特別損失に計上するケースが目につきます。
年金の運用がこれと同じだとは言いませんが、もし当該株式を会社が自ら保有していたらその減損は特別損失で計上していたわけで、これを信託銀行などに運用させただけで、実質は会社として減損が発生している・・・だから特別損失でもいいじゃないか・・・とか。
この考え方の弱いところは、年金で運用しているのだから、それは売買目的の株式であって、減損対象ではないと反論されたらつらい。
要するに、何が言いたいかと言えば、
某国がミサイルを発射しても、それは人工衛星であり、衛星軌道上から将軍様の歌を流していると言い張り、世界中から確認できないと反論されても、「心のきれいな人には、ちゃんと聞こえている」と堂々と真顔で言い返す。
会計とは、厳格に規定されているようですが、法規を見ると、けっこうあいまいな表現が多く、複数の解釈がでる事項がたくさんあります。特別なんだ、臨時なんだよ、という理由を自分なりに明確にできたら、某国のように腹をくくって貫き通す、それが重要だと思います。会計士が6対4でこの処理は無理と思っていても、説明自体がブレず、熱意がこもっていたら、勢いで「今回は認めましょう」となったことは、私の思い込みかもしれませんが、あったと思っています。あくまでも6対4の話ですが。
ただ、今回の特別損失処理は、まともに考えたら難しいように思います。
返信