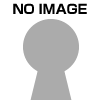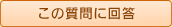編集
私もまだまだ修行の身ですから、以下ご指摘をお願いしたいと思います。
>前に書かれている民事再生法92条では、民事再生申請後以降で尚且つ債権の届出までの期間 と読めるのですが・・・
期限の利益につきましてはご存じの通りで、履行について期限を与えるものであり、この履行期に達するまでは債務不履行にならないという効果があることから、同時にこの時期においては相殺適状にはないと言うことが出来ると思います。
これを反対から見ると、期限の利益を失った場合には相殺適状にあるということになるかと思います。
以上は民法からの視点であり、民再法や破産法から見た場合、期限の利益には言及してはいないようで、単に相殺権について事細かに規定しております。
民再法は破産法とほぼ同じ様な入口をしておりますので、破産法を例に取ってみたいと思いますが、まず、債務者の財産においては「開始手続決定」の裁判がターニングポイントになるようです。
まず、決定後の財産は債務者の自由財産であり、決定前の財産は破産財団に組み込まれます。
原則として自由財産と破産財団は、区別されなければならないようです。
ところで「債権届出期日までに相殺せよ」ですが、これは期限の利益とは関連のない、破産法民再法の効果によるものではと考えられます。
先に述べました「開始手続決定」がキーであり、その裁判以降に起きた決定前の取引等は、決定時に遡及するとされています。(破産法§30)
つまり、破産(再生)債権を一応確定させる債権届出手続は事後になり、この届出の期日をもって確定した債権が破産等債権となるわけであり破産財団に組み込まれます。
組み込まれてしまうと手続を踏まない限り、弁済は通常、出来なくなるのが破産等債権のさだめです。
ところが相殺権において、破産法等は民法よりも相殺可能な範囲を広げているようなんです。
債権者が担保に近い期待権まで失うと辛すぎるだろうと(笑)。
そこで将来の債権までを相殺権に含めた模様です。
ここで手続との関係を整理すると、期限付債権も破産等債権であるが、破産等財団に組み込まれる期日までに相殺を仕掛けるならば、破産等財団へは組み込まれずに、つまり手続を経ることなく相殺が出来ることを何条でしたっけ?、そこで民法の相殺適状に修正を掛けているのではと思うのです。
何か分かりづらいですね :-o
私もまだまだ修行の身ですから、以下ご指摘をお願いしたいと思います。
>前に書かれている民事再生法92条では、民事再生申請後以降で尚且つ債権の届出までの期間 と読めるのですが・・・
期限の利益につきましてはご存じの通りで、履行について期限を与えるものであり、この履行期に達するまでは債務不履行にならないという効果があることから、同時にこの時期においては相殺適状にはないと言うことが出来ると思います。
これを反対から見ると、期限の利益を失った場合には相殺適状にあるということになるかと思います。
以上は民法からの視点であり、民再法や破産法から見た場合、期限の利益には言及してはいないようで、単に相殺権について事細かに規定しております。
民再法は破産法とほぼ同じ様な入口をしておりますので、破産法を例に取ってみたいと思いますが、まず、債務者の財産においては「開始手続決定」の裁判がターニングポイントになるようです。
まず、決定後の財産は債務者の自由財産であり、決定前の財産は破産財団に組み込まれます。
原則として自由財産と破産財団は、区別されなければならないようです。
ところで「債権届出期日までに相殺せよ」ですが、これは期限の利益とは関連のない、破産法民再法の効果によるものではと考えられます。
先に述べました「開始手続決定」がキーであり、その裁判以降に起きた決定前の取引等は、決定時に遡及するとされています。(破産法§30)
つまり、破産(再生)債権を一応確定させる債権届出手続は事後になり、この届出の期日をもって確定した債権が破産等債権となるわけであり破産財団に組み込まれます。
組み込まれてしまうと手続を踏まない限り、弁済は通常、出来なくなるのが破産等債権のさだめです。
ところが相殺権において、破産法等は民法よりも相殺可能な範囲を広げているようなんです。
債権者が担保に近い期待権まで失うと辛すぎるだろうと(笑)。
そこで将来の債権までを相殺権に含めた模様です。
ここで手続との関係を整理すると、期限付債権も破産等債権であるが、破産等財団に組み込まれる期日までに相殺を仕掛けるならば、破産等財団へは組み込まれずに、つまり手続を経ることなく相殺が出来ることを何条でしたっけ?、そこで民法の相殺適状に修正を掛けているのではと思うのです。
何か分かりづらいですね :-o
返信