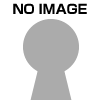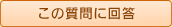いつもお世話になっております。困ったときにしか出てこなくて
申し訳ありませんが、今回もよろしくお願いいたします。
以前賞与引当金について質問し、中小企業会計指針の賞与引当金
繰入額計算法(平成10年度改正前法人税法に規定)について教えて
いただいたのですが、勘違いと、日本語理解力低下により
誤って処理をしていたようです。つきましては、確認のため
いくつか質問させてください。
弊社は5月決算、賞与支給月は8月と12月ですが、賞与支給期間は
規程等で定めていません。(いつからいつの労働分の賞与を
8月に、という形で決めていません)。
賞与額は原則として基本給の2か月分を2回に分けて支給です。
(査定により減額。)
事業開始は昨年4月。昨年5月で決算を迎えた前期中は事業開始準備
をしていたため、給与支給はしましたが、賞与支給はありません。
経理未経験かつ税理士導入せずの方針のため書籍を引きひき決算
処理を行いました。
その際、不十分な理解により、賞与引当金を計上しなければ
いけない、と判断してしまいました。賞与支給日から適当に
判断して1〜6月分を8月支給、7〜12月分を12月支給と解釈し、
8月支給予定分の6分の5(1月から5月までの5か月分)を
賞与引当金として計上してしまいました。
1)平成10年改正前法人税法の賞与引当金繰入の計算式は
繰入額=(前1年間の一人当たりの使用人等に対する賞与支給額
×当期の月数÷12−当期において期末在職使用人等に支給
した賞与の額で当期に対応するものの一人当たりの賞与支給額)
×期末の在職使用人数
なのですが、
前年に賞与を支給した実績がない場合は、賞与引当金を計上しては
いけなかったのでしょうか。いけない場合は今期の決算において
前期損益計上損益で修正すればよいのでしょうか。その場合の
仕訳はどのようになるのでしょうか。
2)賞与引当金の計算ですが、以下のような条件の場合
についてお尋ねします。
(前期)
H20.8月支給賞与 2,000,000円、支給人数15名
H20.12月支給賞与2,250,000円、支給人数20名
(今期)
H21.8月支給賞与 3,680,000円、支給人数18名
H21.12月支給賞与3,840,000円、支給人数24名
今期末在籍人数 33名
・前1年間の一人当たりの使用人等に対する賞与支給額
=2,000,000円÷15 + 2,250,000円÷20
≒245,833.33
・当期の月数 5か月(1月から決算月5月)
・当期において期末在職使用人等に支給した賞与の額で当期
に対応するものの一人当たりの賞与支給額
=(3,680,000円÷18+3,840,000÷24)×(5/12)
=151,851.666
・賞与引当金繰入=(245,833 ×5/12 − 151,851)×33
→マイナスのため引当金計上できない
こういうことになるのでしょうか。
なんだか、職員数が増加している限り賞与引当金が
計上できないようなことになってしましたが、
そういうものなのでしょうか。
単純に計算が間違えているだけなのでしょうか。
長文で申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
いつもお世話になっております。困ったときにしか出てこなくて
申し訳ありませんが、今回もよろしくお願いいたします。
以前賞与引当金について質問し、中小企業会計指針の賞与引当金
繰入額計算法(平成10年度改正前法人税法に規定)について教えて
いただいたのですが、勘違いと、日本語理解力低下により
誤って処理をしていたようです。つきましては、確認のため
いくつか質問させてください。
弊社は5月決算、賞与支給月は8月と12月ですが、賞与支給期間は
規程等で定めていません。(いつからいつの労働分の賞与を
8月に、という形で決めていません)。
賞与額は原則として基本給の2か月分を2回に分けて支給です。
(査定により減額。)
事業開始は昨年4月。昨年5月で決算を迎えた前期中は事業開始準備
をしていたため、給与支給はしましたが、賞与支給はありません。
経理未経験かつ税理士導入せずの方針のため書籍を引きひき決算
処理を行いました。
その際、不十分な理解により、賞与引当金を計上しなければ
いけない、と判断してしまいました。賞与支給日から適当に
判断して1〜6月分を8月支給、7〜12月分を12月支給と解釈し、
8月支給予定分の6分の5(1月から5月までの5か月分)を
賞与引当金として計上してしまいました。
1)平成10年改正前法人税法の賞与引当金繰入の計算式は
繰入額=(前1年間の一人当たりの使用人等に対する賞与支給額
×当期の月数÷12−当期において期末在職使用人等に支給
した賞与の額で当期に対応するものの一人当たりの賞与支給額)
×期末の在職使用人数
なのですが、
前年に賞与を支給した実績がない場合は、賞与引当金を計上しては
いけなかったのでしょうか。いけない場合は今期の決算において
前期損益計上損益で修正すればよいのでしょうか。その場合の
仕訳はどのようになるのでしょうか。
2)賞与引当金の計算ですが、以下のような条件の場合
についてお尋ねします。
(前期)
H20.8月支給賞与 2,000,000円、支給人数15名
H20.12月支給賞与2,250,000円、支給人数20名
(今期)
H21.8月支給賞与 3,680,000円、支給人数18名
H21.12月支給賞与3,840,000円、支給人数24名
今期末在籍人数 33名
・前1年間の一人当たりの使用人等に対する賞与支給額
=2,000,000円÷15 + 2,250,000円÷20
≒245,833.33
・当期の月数 5か月(1月から決算月5月)
・当期において期末在職使用人等に支給した賞与の額で当期
に対応するものの一人当たりの賞与支給額
=(3,680,000円÷18+3,840,000÷24)×(5/12)
=151,851.666
・賞与引当金繰入=(245,833 ×5/12 − 151,851)×33
→マイナスのため引当金計上できない
こういうことになるのでしょうか。
なんだか、職員数が増加している限り賞与引当金が
計上できないようなことになってしましたが、
そういうものなのでしょうか。
単純に計算が間違えているだけなのでしょうか。
長文で申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。