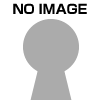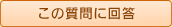編集
ああ、いま読み返して、表現がお粗末だったことに気付きました。
申し訳ない。
「最初の作成者」では、
最初に手形フォームへ必要事項のうちのいくつかを記した者、
に読めてしまいますね・・・。
基本は、確かにこのとおりなのです。
ただ、例外として、白地手形の場合で、
A.金額欄が白地のケースでは、
ここを補充した者(個人事業主、会社など)が手形作成者となります。
B.金額欄の記載があり振出人欄の署名の無い為替手形のケースでは、
引受人欄等に最初に署名した者が手形作成者となります。
C.引受人欄等への署名があり金額欄・振出人欄ともに白地の場合には、
振出人欄への署名が先におこなわれればAで、
金額欄への記入が先におこなわれればBで、
判定することになります。
実務上でありがちなのは、
金額と引受人欄は記入して振出人欄が白地(空欄)のまま
為替手形を発行するパターンでして、
この場合、上記Bのとおり、
引受人欄を記入した「最初の作成者」に納税義務が課せられます。
dio960さんのケースが、正にこれですね。
このときに、
振出人欄を記入した者が印紙を添付し消印をしたならば、
この者には納税義務がありませんから、
添付消印をした額だけ、先に引受人欄を記入した者へ請求出来ます。
これは、相手の得た「不当利得」の返還請求ってやつでして、
民法で「請求出来るよ」と保証されています。
(「不当」といっても、いい・悪いの価値観はほとんど入っておりません。)
ただ、実務上は請求困難でしょうから、
例えば原価積み上げ方式で見積り額を算定している場合には、
見積りの段階で、見積り額に印紙代分も上乗せしておくことも
少なくないかと思います。
kei8さんお書きの寄附金か売上値引かという税務上の問題点については、
この不当利得返還請求を放棄したときに始めて生じる問題ですね。
ああ、いま読み返して、表現がお粗末だったことに気付きました。
申し訳ない。
「最初の作成者」では、
最初に手形フォームへ必要事項のうちのいくつかを記した者、
に読めてしまいますね・・・。
基本は、確かにこのとおりなのです。
ただ、例外として、白地手形の場合で、
A.金額欄が白地のケースでは、
ここを補充した者(個人事業主、会社など)が手形作成者となります。
B.金額欄の記載があり振出人欄の署名の無い為替手形のケースでは、
引受人欄等に最初に署名した者が手形作成者となります。
C.引受人欄等への署名があり金額欄・振出人欄ともに白地の場合には、
振出人欄への署名が先におこなわれればAで、
金額欄への記入が先におこなわれればBで、
判定することになります。
実務上でありがちなのは、
金額と引受人欄は記入して振出人欄が白地(空欄)のまま
為替手形を発行するパターンでして、
この場合、上記Bのとおり、
引受人欄を記入した「最初の作成者」に納税義務が課せられます。
dio960さんのケースが、正にこれですね。
このときに、
振出人欄を記入した者が印紙を添付し消印をしたならば、
この者には納税義務がありませんから、
添付消印をした額だけ、先に引受人欄を記入した者へ請求出来ます。
これは、相手の得た「不当利得」の返還請求ってやつでして、
民法で「請求出来るよ」と保証されています。
(「不当」といっても、いい・悪いの価値観はほとんど入っておりません。)
ただ、実務上は請求困難でしょうから、
例えば原価積み上げ方式で見積り額を算定している場合には、
見積りの段階で、見積り額に印紙代分も上乗せしておくことも
少なくないかと思います。
kei8さんお書きの寄附金か売上値引かという税務上の問題点については、
この不当利得返還請求を放棄したときに始めて生じる問題ですね。
返信