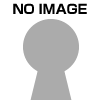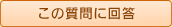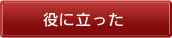編集
どうやら、金庫の現金を数えて来いというような、不正暴きではないようですので、
私も人に教えられるような知識や経験が豊富なわけではありませんが、
1.業務のフローが明確で、ポイントごとに複数のチェックがかかるシステムがあるかどうか
2.そのシステムが有効かつ適正に機能しているかどうか
このような観点で調査するというのはいかがでしょうか?
1.については、受注から出荷、売上計上までの流れ、逆に、発注から入荷、仕入れ計上までの流れなどについて、誰がどの時点でどのようなデータを作成し、誰に流すのかをヒアリングして、まず業務フローをつかむ。次に、例えば受注エントリーは、誰が確認するのか、何のチェックもないまま流れないか、架空売上、重複計上、エントリーもれ、受注の電話の聞き間違い・・・これらに何らかの押さえが効いているか。このような人間のチェックに加え、例えば、受注エントリーがない製品は、コンピュータ上、いくら出荷をしようとしても入力できないとか、そういうシステム的な押さえがあるか。
2.実際に、ランダムに売上や入荷の実例を取り上げて、この取引に関する、納品書や請求書その他の伝票や台帳をすべて揃えさせて、本当にフローに沿って処理がされているか、検印がもれていないかなど、絵に書いた餅でないかどうか確認する。
注意点は、月末の売上です。ノルマ達成のために押し込みで出荷したことにして、翌月にマイナスを計上しているような古典的な粉飾のチェックでしょうね。売り上げ計上の基準が不明確であれば明確にさせねばなりません。
印鑑もなく、聞いた事がないような得意先への売上は、横流しかもしれません。また、長期にわたり回収されていない売掛金は、しっかり督促させねばなりません。
いくらでもあるのですが、系統立ててうまく説明できません。すみません。
監査の教科書でも立ち読みしてください。
どうやら、金庫の現金を数えて来いというような、不正暴きではないようですので、
私も人に教えられるような知識や経験が豊富なわけではありませんが、
1.業務のフローが明確で、ポイントごとに複数のチェックがかかるシステムがあるかどうか
2.そのシステムが有効かつ適正に機能しているかどうか
このような観点で調査するというのはいかがでしょうか?
1.については、受注から出荷、売上計上までの流れ、逆に、発注から入荷、仕入れ計上までの流れなどについて、誰がどの時点でどのようなデータを作成し、誰に流すのかをヒアリングして、まず業務フローをつかむ。次に、例えば受注エントリーは、誰が確認するのか、何のチェックもないまま流れないか、架空売上、重複計上、エントリーもれ、受注の電話の聞き間違い・・・これらに何らかの押さえが効いているか。このような人間のチェックに加え、例えば、受注エントリーがない製品は、コンピュータ上、いくら出荷をしようとしても入力できないとか、そういうシステム的な押さえがあるか。
2.実際に、ランダムに売上や入荷の実例を取り上げて、この取引に関する、納品書や請求書その他の伝票や台帳をすべて揃えさせて、本当にフローに沿って処理がされているか、検印がもれていないかなど、絵に書いた餅でないかどうか確認する。
注意点は、月末の売上です。ノルマ達成のために押し込みで出荷したことにして、翌月にマイナスを計上しているような古典的な粉飾のチェックでしょうね。売り上げ計上の基準が不明確であれば明確にさせねばなりません。
印鑑もなく、聞いた事がないような得意先への売上は、横流しかもしれません。また、長期にわたり回収されていない売掛金は、しっかり督促させねばなりません。
いくらでもあるのですが、系統立ててうまく説明できません。すみません。
監査の教科書でも立ち読みしてください。
返信