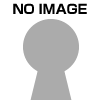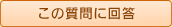編集
>でも、父親が息子に証明書を渡すと言う事は、息子さんが年末調整の事務をする方に父親が支払っていると言うからダメで、黙っていればOKと言う事ですか?
はっきり言わせて頂くと、その通りなのです!!!
税務署も提出された全ての人の分について「実質支払者が誰か」まで調査することは不可能なのです。
それを逆手にとって提出者(従業員)も経理担当者も暗黙の了解で、あるいは目をつむってそのまま提出している場合も相当数あると思いますよ。
もしこれが判明するとすれば会社では税務調査しかありませんが、税務調査ではそんな小さなことまでやりませんから。(私の経験では過去一度もありません。)
>コールセンターみたいなとろこにつながり
これは国税庁の電話相談室です。
>生命保険の契約者が母親だと納税者が支払っている証拠はどこにありますか?と聞かれ自己申告ですと答えましたらそれはダメですと…
これについては異議のあるところです。
国税庁ですので建前論を言っています。単なる口頭ではダメです という意味合いですね。
実質的に誰が支払っているかの証拠の提示が必要かどうかは書かれていません。契約者が支払っているとは必ずしも限りません。
あくまでも要件を満たす保険の費用負担している人の税額から控除しましょう という趣旨です。
納税者の自己申告とのことですが、それを証明できるものがあれば認められます。
たとえば、納税者の預金口座から自動引き落としされていればその写しなど、あるいは現金払いならば領収書などです。
ですから、
>先週「年末調整の説明会」があり税務署の職員に確認したら対象になると言われていたんです!!・・実際はこれが妥当な結論です。
上司の方はどの部分でダメだといっているのでしょうかね。
ここからは保険料控除に関する私見で恐縮ですが、長きにわたり昔からなぜ民間会社の生命保険や損害保険だけが年末調整の対象になるのでしょうね。(住宅取得借入のもありますが)
これが無ければ年末調整作業がどれだけ楽になることか・・・事務方の作業量は半減するはずです!!
はっきり言ってこれほどザル処理されて一般化しているものも珍しいと思いますよ。
いい加減、政府も保険会社との関係を考え直してはどうかと思っています。
この通信情報・ITの進んだ時代に、保険料分の控除など保険会社と個人との間で処理する方法を構築して実行すれば良い話です。
何と言っても昔から保険会社と契約個人間で配当金等のやり取りの仕組みはある訳ですから、それを利用すれば良いだけのことですよね。
またはこれほど保険が浸透したのに未だにこの「商品」に優遇税制を設けていること自体、業界との癒着以外の何物でもないでしょう。
いつまでも政府が保険業界を取り込んでいる時代ではないでしょう。
以上、ついつい毎年この時期に想う愚痴でした(苦笑)!
失礼致しました。。。
<追伸>
書き忘れてしまいましたが、この後の処理についてですが、
この保険料を本当に納税者(御社の従業員さん)が支払っていて、保険料の限度額の範囲に入るのであれば、上述のようにその証拠があれば上司も認めてくれるでしょうから、その場合は問題なく年末調整対象となるでしょう。
それでも上司が認めなかった場合には年末調整もできないと思われますので、その場合にはご本人にお話しされて来年2月の確定申告で証拠書類を添えれば認められると思いますよ。
そうなれば来年の年末調整時には「確定申告でみとめられましたから」ということで以後はOKとなると思います。
個人の税金に関することは本来は個人の責任においてなされるものです。
ですから確定申告が本筋ですが、それを全て受け付けると税務署側で手に負えないために会社の従業員の場合には年末調整という方法でその提出を会社が代行しているにすぎませんから。
弊社では年末調整書類を配布する際の文書に、この件について「誰が実質の支払者であるかがポイントです」と、「虚偽申告の場合には後日、追徴課税される場合がありますのでご注意下さい」という文言を必ず入れています。
長文お詫び申し上げます。
>でも、父親が息子に証明書を渡すと言う事は、息子さんが年末調整の事務をする方に父親が支払っていると言うからダメで、黙っていればOKと言う事ですか?
はっきり言わせて頂くと、その通りなのです!!!
税務署も提出された全ての人の分について「実質支払者が誰か」まで調査することは不可能なのです。
それを逆手にとって提出者(従業員)も経理担当者も暗黙の了解で、あるいは目をつむってそのまま提出している場合も相当数あると思いますよ。
もしこれが判明するとすれば会社では税務調査しかありませんが、税務調査ではそんな小さなことまでやりませんから。(私の経験では過去一度もありません。)
>コールセンターみたいなとろこにつながり
これは国税庁の電話相談室です。
>生命保険の契約者が母親だと納税者が支払っている証拠はどこにありますか?と聞かれ自己申告ですと答えましたらそれはダメですと…
これについては異議のあるところです。
国税庁ですので建前論を言っています。単なる口頭ではダメです という意味合いですね。
実質的に誰が支払っているかの証拠の提示が必要かどうかは書かれていません。契約者が支払っているとは必ずしも限りません。
あくまでも要件を満たす保険の費用負担している人の税額から控除しましょう という趣旨です。
納税者の自己申告とのことですが、それを証明できるものがあれば認められます。
たとえば、納税者の預金口座から自動引き落としされていればその写しなど、あるいは現金払いならば領収書などです。
ですから、
>先週「年末調整の説明会」があり税務署の職員に確認したら対象になると言われていたんです!!・・実際はこれが妥当な結論です。
上司の方はどの部分でダメだといっているのでしょうかね。
ここからは保険料控除に関する私見で恐縮ですが、長きにわたり昔からなぜ民間会社の生命保険や損害保険だけが年末調整の対象になるのでしょうね。(住宅取得借入のもありますが)
これが無ければ年末調整作業がどれだけ楽になることか・・・事務方の作業量は半減するはずです!!
はっきり言ってこれほどザル処理されて一般化しているものも珍しいと思いますよ。
いい加減、政府も保険会社との関係を考え直してはどうかと思っています。
この通信情報・ITの進んだ時代に、保険料分の控除など保険会社と個人との間で処理する方法を構築して実行すれば良い話です。
何と言っても昔から保険会社と契約個人間で配当金等のやり取りの仕組みはある訳ですから、それを利用すれば良いだけのことですよね。
またはこれほど保険が浸透したのに未だにこの「商品」に優遇税制を設けていること自体、業界との癒着以外の何物でもないでしょう。
いつまでも政府が保険業界を取り込んでいる時代ではないでしょう。
以上、ついつい毎年この時期に想う愚痴でした(苦笑)!
失礼致しました。。。
<追伸>
書き忘れてしまいましたが、この後の処理についてですが、
この保険料を本当に納税者(御社の従業員さん)が支払っていて、保険料の限度額の範囲に入るのであれば、上述のようにその証拠があれば上司も認めてくれるでしょうから、その場合は問題なく年末調整対象となるでしょう。
それでも上司が認めなかった場合には年末調整もできないと思われますので、その場合にはご本人にお話しされて来年2月の確定申告で証拠書類を添えれば認められると思いますよ。
そうなれば来年の年末調整時には「確定申告でみとめられましたから」ということで以後はOKとなると思います。
個人の税金に関することは本来は個人の責任においてなされるものです。
ですから確定申告が本筋ですが、それを全て受け付けると税務署側で手に負えないために会社の従業員の場合には年末調整という方法でその提出を会社が代行しているにすぎませんから。
弊社では年末調整書類を配布する際の文書に、この件について「誰が実質の支払者であるかがポイントです」と、「虚偽申告の場合には後日、追徴課税される場合がありますのでご注意下さい」という文言を必ず入れています。
長文お詫び申し上げます。
返信