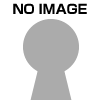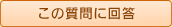編集
概ね貝様と同じ立場から、重要でない補足をちょっとだけ。
「特別利害関係人」及び「著しく不当」の範囲は争いの余地があります。与えられた情報だけでは即断できません。
仮に本件引受人が特別利害関係人だとしても、株主総会には問題なく参加できます。これを禁止する規定がないからです。実は昔は禁止されてましたが、昭和56年の商法改正で政策転換されたものです。「事前の排除」を廃止するかわりに「取消請求」が導入されたわけです。
少数株主の対抗手段としては、新株発行の無効の訴え(828条1項2号)と言う手も一応用意されています。
質問の趣旨から外れますが、「割当先が議決権に加われると、決定してしまう」ことから、この株主は既に2/3を確保しており、本件増資の目的は専ら純粋な資金調達にあると推察します。
もしそうであれば第三者割当にこだわらず、株主割当を検討する価値があると感じます。そうすればトラブルの可能性は100%なくせます故。
概ね貝様と同じ立場から、重要でない補足をちょっとだけ。
「特別利害関係人」及び「著しく不当」の範囲は争いの余地があります。与えられた情報だけでは即断できません。
仮に本件引受人が特別利害関係人だとしても、株主総会には問題なく参加できます。これを禁止する規定がないからです。実は昔は禁止されてましたが、昭和56年の商法改正で政策転換されたものです。「事前の排除」を廃止するかわりに「取消請求」が導入されたわけです。
少数株主の対抗手段としては、新株発行の無効の訴え(828条1項2号)と言う手も一応用意されています。
質問の趣旨から外れますが、「割当先が議決権に加われると、決定してしまう」ことから、この株主は既に2/3を確保しており、本件増資の目的は専ら純粋な資金調達にあると推察します。
もしそうであれば第三者割当にこだわらず、株主割当を検討する価値があると感じます。そうすればトラブルの可能性は100%なくせます故。
返信