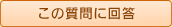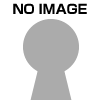編集
第三者割当で、かつ総数引き受け契約を使わないなら、
引受の申し込みをした人に割り当てる、という
仕組みは動かしがたいので、
法に書いてある順番通りに手続きを進めるなら緑、
昔の第三者割当のように、株主総会にかける前に
割当先も取締役会で決議するスタイルを
特に望むなら青、という感じです。
(というか、青のルートにするのは、
特に取締役会非設置の会社で、
募集事項決定の株主総会の後に、
もう一回割当の株主総会を開くのが面倒くさい
というのが主な理由じゃないかな、と思います)
どちらでやるべきということでもないのでしょうが、
青のルートは細工が多いので、どこかに穴があると
例えば登記の段階で頓挫するかもしれません。
非公開の取締役会設置会社だと、株主総会の
招集通知書(予め株主の承諾を取っていれば
電子メールで代替可)を発してから
総会当日までの間に1週間以上空けるのが
原則です。(299条)
株主が全員居合わせているような状況なら、
同意を取ってその場で即開催を決める、
ということも可能です。(300条)
株主全員から同意を取って、法定の期間より
短い期間で株主総会を招集するということも
実務では行われていますが、
書面が往復する時間を考えると
もともと1週間のところを短縮する余地は
それほどないという気もします。
取締役会の招集から開催までも原則は1週間ですが、
定款で短縮していればその日数になります。
こちらも取締役(および、監査役設置会社なら監査役も)の
全員が居合わせれば同意を取って
その場で開催を決めることが可能です。(368条)
遠方の人がおらず全員出社できる状況なら、
即時開催はそれほど困難ではないと思います。
(但し、先のレスでちょっと触れた「欠席」というのは
有り得ないことになりますが・・・)
第三者割当で、かつ総数引き受け契約を使わないなら、
引受の申し込みをした人に割り当てる、という
仕組みは動かしがたいので、
法に書いてある順番通りに手続きを進めるなら緑、
昔の第三者割当のように、株主総会にかける前に
割当先も取締役会で決議するスタイルを
特に望むなら青、という感じです。
(というか、青のルートにするのは、
特に取締役会非設置の会社で、
募集事項決定の株主総会の後に、
もう一回割当の株主総会を開くのが面倒くさい
というのが主な理由じゃないかな、と思います)
どちらでやるべきということでもないのでしょうが、
青のルートは細工が多いので、どこかに穴があると
例えば登記の段階で頓挫するかもしれません。
非公開の取締役会設置会社だと、株主総会の
招集通知書(予め株主の承諾を取っていれば
電子メールで代替可)を発してから
総会当日までの間に1週間以上空けるのが
原則です。(299条)
株主が全員居合わせているような状況なら、
同意を取ってその場で即開催を決める、
ということも可能です。(300条)
株主全員から同意を取って、法定の期間より
短い期間で株主総会を招集するということも
実務では行われていますが、
書面が往復する時間を考えると
もともと1週間のところを短縮する余地は
それほどないという気もします。
取締役会の招集から開催までも原則は1週間ですが、
定款で短縮していればその日数になります。
こちらも取締役(および、監査役設置会社なら監査役も)の
全員が居合わせれば同意を取って
その場で開催を決めることが可能です。(368条)
遠方の人がおらず全員出社できる状況なら、
即時開催はそれほど困難ではないと思います。
(但し、先のレスでちょっと触れた「欠席」というのは
有り得ないことになりますが・・・)
返信