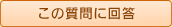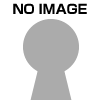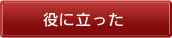編集
皆様、お返事ありがとうございました。
その後、税務署に問い合わせたところ「今回の場合、(コンピュータのプログラムという作業では源泉が発生することもありますが。)外注先の方が全ての責任を負っている(弊社は仲介役のみですので・・・。)ので、作業をされている個人の方が確定申告をすれば良いことになります。したがって、源泉の必要はありません。徴収してしまった所得税に関しては、本人に返すかもしくはいったん納付していただいて、本人が還付申請をするかどちらかを選んでください。」とのことでした。
preにはそのように伝え、本人に直接返すことになりました。
解決いたしましたので、一応ご報告まで。
ありがとうございました。 :-D
皆様、お返事ありがとうございました。
その後、税務署に問い合わせたところ「今回の場合、(コンピュータのプログラムという作業では源泉が発生することもありますが。)外注先の方が全ての責任を負っている(弊社は仲介役のみですので・・・。)ので、作業をされている個人の方が確定申告をすれば良いことになります。したがって、源泉の必要はありません。徴収してしまった所得税に関しては、本人に返すかもしくはいったん納付していただいて、本人が還付申請をするかどちらかを選んでください。」とのことでした。
preにはそのように伝え、本人に直接返すことになりました。
解決いたしましたので、一応ご報告まで。
ありがとうございました。 :-D
返信